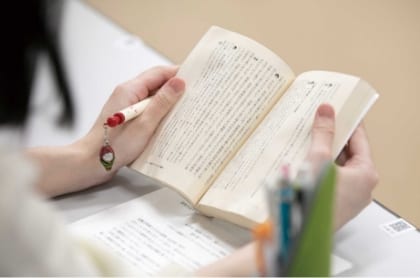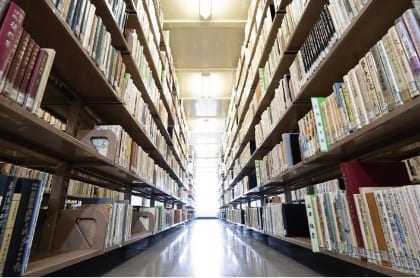学科概要人文社会科学を学際的?総合的に学ぶ
文化総合学科では、高校で学ぶ社会科系科目の内容を発展的、かつ広範に学ぶことができます。
「現代社会」専修と「歴史?思想」専修という二つの専修を行き来しながら、
21世紀の諸問題に柔軟に対応し、主体的に生きるための知性や精神性をバランスよく習得することを目指します。


専修
- 「現代社会」専修
- 高校の「政治?経済」の内容にあたる〈法学〉〈国際関係論〉に加え、現代社会の理解に有益な〈異文化コミュニケーション論〉〈文化人類学〉〈心理学〉から構成されています。現代の社会と文化について、その制度の仕組みや働きを、社会に住む人びとの考え方やコミュニケーションのあり方をみながら、多面的に研究します。
* 新学習指導要領の「公共」「政治経済」の延長に〈法学〉〈国際関係論〉があります。
- 「歴史?思想」専修
- 高校の「日本史」の延長にある〈日本史(古代?中世)〉〈日本史(近世?近代)〉、「世界史」の延長にある〈西洋史〉、「倫理」の延長にある〈哲学〉と〈倫理学〉から構成されています。現代の社会と文化について、その成り立ちから理解するために、背景や基盤となっている歴史?思想を研究します。
* 新学習指導要領の「歴史総合」「日本史探究」の延長に〈日本史(古代?中世)〉〈日本史(近世?近代)、「歴史総合」「世界史探究」の延長に〈西洋史〉、「公共」「倫理」の延長に〈哲学〉〈倫理学〉があります。
学科の目指すもの
文化総合学科は、「現代社会」専修と「歴史?思想」専修から構成されています。これら二つの専修を横断する学際的な学びを通して、複雑な社会や文化を多面的に捉えることを目指します。
学際的とは、ある研究テーマに対して、特定の学問分野の単一の視点から探求していくのではなく、様々な学問分野を横断した複数の視点や方法から探求していくことを指します。
たとえば、文化総合学科では、ジェンダー、貧困、差別、環境問題、先住民族の権利といった世界が取り組む社会的課題について、異文化コミュニケーション、法律、政治、文化、心理学、歴史、思想といった多様な視点から学んでいくことができます。
このような人文社会科学を中心とした文化総合学科の学びを通じて、現在の社会や文化について学術的な知識を深めるのみならず、その歴史的経緯や背景的思想といった成り立ちを含めて理解することが可能となります。そのうえで、新たな時代をしっかりとした視点でとらえられる人材の育成をめざします。
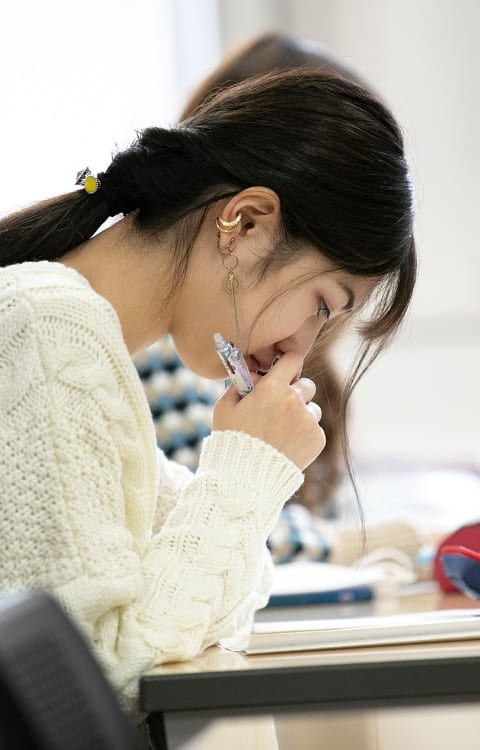

学びのポイント

一つの学問分野を追求しながら
他分野も学べるカリキュラム
文化総合学科では、入門的な授業から専門的な講義や演習へ、体系的に学べるカリキュラムを設計しています(「カリキュラムマップ」をご参照ください)。
そのなかでは、1年次の基礎演習から4年次の卒業研究演習まで、同一の専任教員の演習を4年間通して履修することが可能となっています。一つの学問分野について、初歩的な知識をまずは身につけ、そこから専門的な研究へと段階的にたどれるようになっています。
もちろん、一つの分野だけではなく、二つの専修をまたいだ履修や専修の途中変更も可能です。多様な学問分野に触れながら、大学4年間を通してどの学問分野に専念していくのかじっくり決めていくことができるのが文化総合学科の魅力です。
外国語と外国社会の知識
双方を習得できる
文化総合学科では、英語のみならず中国語や韓国語などの運用能力を高められるカリキュラムを用意しています。
また、特定の外国語の学習を進めながら、中国や韓国、さらにはイギリス、ドイツ、フランスといった各国の「文化史」や「文化論」を学ぶことができます。
文化総合学科では、外国語と外国社会に関する知識という、国際社会での活躍に必要な双方の知識を習得することが可能です。
自分で選んだテーマを学際的に追及
卒業後のキャリア形成につながる経験
文化総合学科は、現代社会やそれにつながる歴史?思想について、専門性を保持しつつも学際的に学ぶことができる学科です。
複雑化し、価値観の多様化が常識となっている現代社会でキャリアを積んでいくにあたって、文化総合学科での「学際的」な学びはますます重要となってくるでしょう。なぜならば、多様な人びとと理解を共有しつつ協働していく姿勢、多様な視点からの批判的検討が、複雑さを増す現代社会で活躍するにあたってこれから一層必要になると考えられるからです。
文献精読、批判的読解、史料調査、統計分析、フィールドワーク、インタビューと、幅広い学問分野とその「学び方」に親しめることも文化総合学科の特長です。先行き不透明で流動的な現代社会では卒業後も新たな知識獲得が求められますが、そのための「学びの基礎」を身につけることができます。
こうした文化総合学科の学際的な「学びの成果」と「学び方」を活かして、多くの卒業生が様々な分野で活躍しています。
取得可能な免許?資格文化総合学科で取得可能な免許?資格は以下の通りです。
- 高等学校教諭一種免許状(地理歴史?公民)
- 中学校教諭一種免許状(社会)
- 司書(任用資格)
- 司書教諭(任用資格)
- 学校司書
- 日本語教師